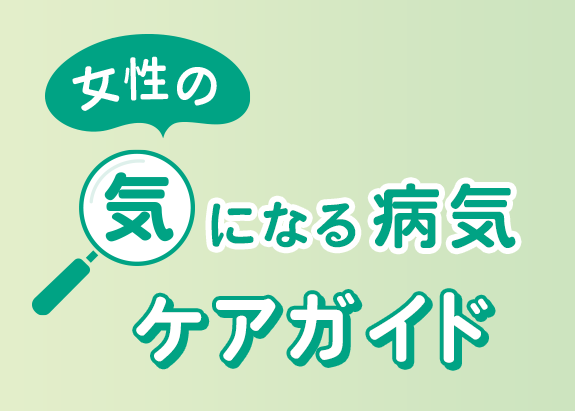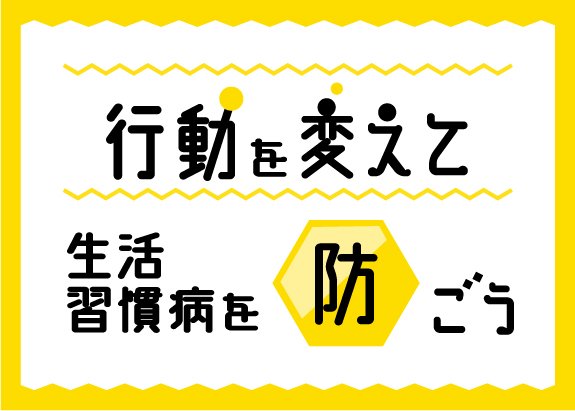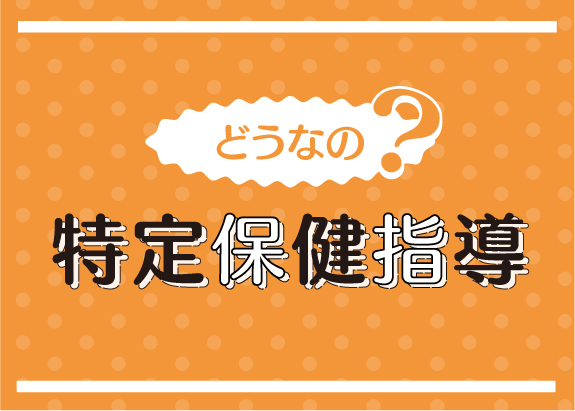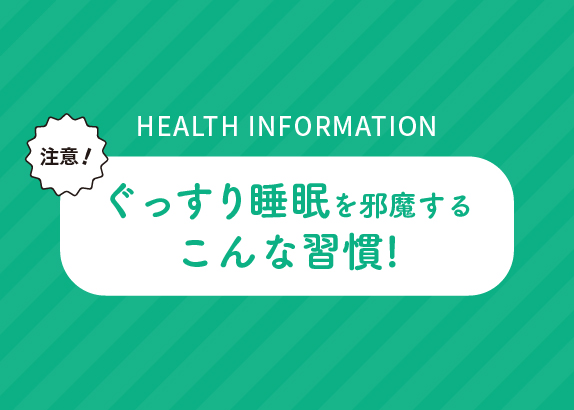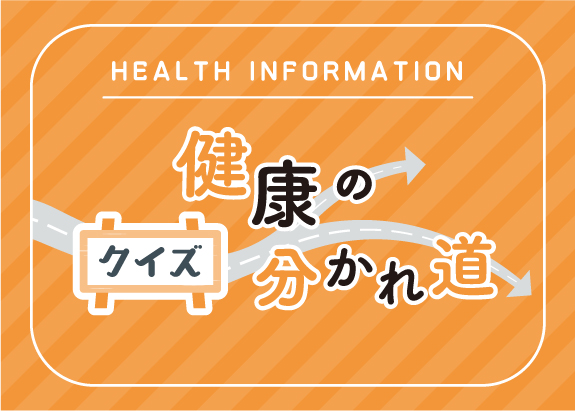健康情報
心を強くする 思考力の鍛え方
「決断疲れ」の対処法
テレビ、ネット、雑誌など、黙っていてもあらゆる情報が目に飛び込んでくる現代社会。選択肢が多すぎて「決断疲れ」したときの対処法を紹介します。

脳を使いつづけると精神は疲れていく
私たちは朝目覚めた瞬間から夜眠りにつくまで、無意識のうちに何万回もの〝選択〟をくり返しています。たとえば朝起きてストレッチをするか二度寝をするか、どちらの服を着て出かけようか、お昼ごはんは何を食べようか、夕食後は何をしようか、何時に布団に入ろうか─。
日常のあらゆる場面で決断を求められると、それが積み重なることで脳はどんどん疲れていきます。これが「決断疲れ」と呼ばれるものです。スタンフォード大学経営大学院のレヴァヴによれば、「からだを使いつづけていると疲労するのと同じように、脳も使いつづけると精神が疲れる」のだといいます。
このレヴァヴが、ネゲヴ・ベン=グリオン大学のダンジガーらと行った調査を紹介します。彼らは、イスラエルの刑務所で裁判官によって下される「仮釈放の決定」について調査し、1年間で1100件以上あった決定を分析したところ、ある一つのパターンがみえてきました。裁判官たちの仮釈放の可否判断を左右するのは、受刑者の人種や民族的背景、さらには犯罪の内容ではなく、「時間帯」だったというのです。
午前中の早い時間帯に仮釈放の可否を判断された受刑者は約65%が仮釈放を認められたのに対し、時間がたつにつれて、その確率は0%に近くなっていきました。しかし、裁判官たちが食事休憩をしたあとは、再び65%に戻ったのです。この実験結果は、決断のプロである裁判官でさえ時間とともに精神的な疲労を感じ、決断する力が低下することを示しています。
情報があふれる現代。自ら意識的に情報を取りに行かずとも、スマートフォンを開けば次々と新しいニュースやSNSの投稿、広告などが目に飛び込んできます。17世紀のイギリス人紳士が一生をかけて得る情報よりも、現在のニューヨークタイムズ紙1日分に掲載されている情報のほうが多いという話もあるほどです。
情報がふえ、選択肢がふえることは、とても便利なことです。その半面、自分にとって何が最善なのかを見失ったり、正しい判断を見誤ってしまう可能性があるという事実を忘れないようにしておくことも重要でしょう。
「こんなときはこうする」と選択のルールを決める
情報が多いと判断を誤るという典型的な例が、アムステルダム大学のダイクスターハウスらの実験で示されています。
この実験では、被験者に考える時間をたっぷり与えるグループAと、パズルをさせて考える時間を意図的に奪うグループBに分け、何台かある中古車のなかからお買い得な1台を選ばせました。対象となる車の数が4台のときには、両グループに大きな差はありません。ところが台数が12台にふえると、考える時間が多かったグループAは、お買い得な車を選ぶ割合が25%以下に低下し、考える時間が短かったグループBは60%の被験者が正解を選ぶことができたのです。この実験結果からは、情報が多かったり、考える時間が長すぎたりすると、人は間違った決断をしやすいということが示されています。
そんな決断疲れに陥りがちな現代の生活のなかで、より効率的に、よりよい判断をしていく方法は、できるだけ考えないですむように、決めるためのルールをあらかじめ設定しておくことです。
たとえばレストランに入ってメニューの選択肢があまりにたくさんあると、どれを選べばよいのか迷ってしまいます。そんなときは、「おすすめと書いてある品を選ぶ」「日替わり定食を頼む」というルールを設定しておくわけです。同じように、着ていく服に迷ったら「晴れている日は寒色系、曇りなら暖色系」のように決めておきます。情報に触れる量を制限するのも一つの方法です。
また、ふだんから情報に触れすぎないようにすることも大切です。退屈だとついスマホをいじってしまいますが、スマホを触る代わりに散歩に出る、電車のなかではあえて目を閉じて視覚情報をすべてシャットアウトするなど、「こんなときはこうする」というルールを考えておくとよいでしょう。
Profile
明治大学法学部教授「法と言語科学研究所」代表
堀田 秀吾
専門は社会言語学、理論言語学、心理言語学など。研究においては法におけるコミュニケーションに関して、言語学、心理学、法学、脳科学などさまざまな分野の知見を融合したアプローチで分析を展開している。